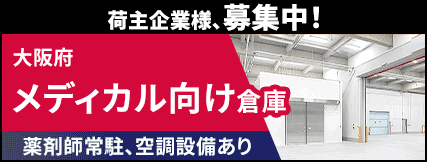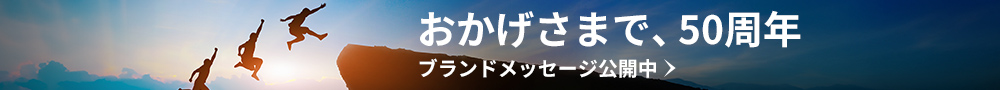危険物倉庫サービス

危険物物流の需要増に応え、法令遵守の倉庫インフラを提供
近年、日々の生活や事業活動に欠かせない製品のなかには、法律で「危険物」として指定され、その保管や取り扱いに専門的な管理が義務付けられるものが増えています。特に、電気自動車(EV)や各種電子機器に利用されるリチウムイオン電池、また需要が拡大している消毒用アルコールなどがその代表例と言えるでしょう。
消防法では、これらの危険物を一定数量以上保管する場合、火災予防のために厳しく定められた基準を満たす「危険物倉庫」で管理することが必須とされています。企業のコンプライアンス意識の高まりも背景に、国内市場では法令を遵守できる危険物倉庫の需要が非常に高まっており、供給が追い付かない状況も生まれています。

このような旺盛な需要にお応えするため、当社では危険物倉庫の能力増強を積極的に進めております。長年にわたり培ってきたノウハウと徹底した安全体制に基づき、お客様の多種多様な危険物を、関連法規を遵守して安全かつ確実に保管・管理いたします。
危険物第4類 取扱品例
塗料、溶剤、オイル、電池、化学原料など、幅広い危険物に対応。第4類(引火性液体)の保管ニーズに安全・確実にお応えします。
イオン電池
原料など
など
(油入り)
ギアオイル
灯油、軽油、キシレン、クロロベンゼン、n-ブチルアルコール、酢酸、プロピオン酸、アクリル酸、トルエン、イソプロピルアルコール(IPA)、ブタノール、エチルアセテート、メチルイソブチルケトン(MIBK)、プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)、メチルシクロヘキサン、酢酸ブチルなど
重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼン、エチレングリコール、グリセリン、フェノール、クレゾール、アクリルアミド、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール、トリエタノールアミン、グアニジンなど
ギアー油、シリンダー油、ポリエチレングリコール(PEG)、シリコーンオイル、エポキシ樹脂硬化剤、炭化水素オイル、ジエチルヘキシルフタレート(DEHP)、ジオクチルアジペート(DOA)、炭酸エチレン(EC)、ジメチルカーボネート(DMC)、ジエチルカーボネート(DEC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、リン酸エステル系難燃剤など
ヤシ油、パーム油、オリーブ油、ヒマシ油、落花生油、ナタネ油、米ぬか油、ゴマ油、綿実油、トウモロコシ油、ニシン油、大豆油、ヒマワリ油、キシ油、イワシ油、アマニ油、エノ油、ホホバオイル、ココナッツオイル、サフラワー油、月見草油、ラノリン、シアバターなど
危険物倉庫 拠点紹介

BCP対策や広域出荷に対応する柏崎拠点
1. BCP(事業継続計画)対策としての分散保管
関東に集中しがちな危険物保管拠点の“分散立地”として、地震・災害リスクの地域偏りを回避するBCP対応に有効です。
2. 首都圏・関西圏への中継にちょうどよい距離
柏崎市は新潟県の中部に位置しており、日本海側の中間拠点として、首都圏(関東)と関西圏のどちらにもアクセスしやすい立地です。広域出荷や幹線輸送の中継基地として機能します。

3. 冬季も比較的安定した物流運用が可能
新潟県内でも豪雪エリアを避けたエリアに位置しており、北陸道・国道8号・JR越後線など交通網が整備されているため、冬季も物流が止まりにくい点は運用上の安心材料になります。また、事務所棟は省エネ基準を満たす仕様の断熱材を設置し、敷地内には消雪用散水設備も完備しています。
3. 製造・研究拠点との連携に最適
新潟県内には化学品・電池材料・精密機器などの製造業の工場や研究施設が点在しており、原材料や製品の保管・調整在庫の置き場として活用しやすい立地です。 特に県内・北陸圏のメーカーとの相性が良好です!
最大限の保管効率と安全性を両立した危険物倉庫
1. 大量保管に対応した高い収容力
同一貨物のパレタイズ保管に対応。2棟合計で最大2,550パレットを保管可能。1パレットあたり最大900kgまで対応。
2. 倉庫スペースを無駄なく活用
サイドフォークリフトの導入により、通路幅を最小限に抑え、限られた面積でも最大限の保管効率を実現。

3. 防爆仕様の設備で安全性を確保
サイドフォークリフトは危険物保管に適した防爆仕様を採用。可燃性ガスや粉塵による爆発リスクを低減。
4. 環境配慮型の構造
フォークリフトはすべて排ガスゼロの電動式。事務所棟は断熱材や高効率照明など省エネ基準を満たす仕様。
5. 施設内の効率的な動線設計
各棟のレイアウトは荷役機器の動きを考慮し、保管から搬出までの安全性と効率を高める構造設計。
危険物倉庫に関してよくあるご質問
まずは以下までお声がけ下さい!1営業日以内に担当より御連絡差し上げます。
SBS東芝ロジスティクス(株)
営業戦略部
TEL:050-1741-3075
(土日祝を除く AM9:00~PM5:00)
危険物倉庫とは?
危険物の分類と危険物倉庫の役割
消防法では、引火・爆発・酸化などの性質を持つ物質を「危険物」として第1類から第6類に分類しています。たとえば、酸化性物質は第1類、可燃性ガスは第2類、自然発火性物質は第3類、そして引火性液体類を扱うのが第4類です。塗料や溶剤、オイル類、アルコール類など、多くの産業製品がこの第4類に該当します。危険物倉庫は、これらを法令で定められた構造・設備・管理基準に基づいて安全に保管するための専用施設であり、一般倉庫とは区別されています。

危険物倉庫の需要が高まる背景
近年、日常生活や産業活動に欠かせない製品の中には、法律で「危険物」として指定されるものが増えています。特に、リチウムイオン電池や電子機器用の電解液、消毒用アルコール類などは、火災リスクを伴うため適正な保管が求められています。消防法では、これらの危険物を一定数量以上保管する場合、厳格な基準を満たした危険物倉庫での管理が義務化されています。また、企業のコンプライアンス意識やBCP(事業継続計画)への対応強化を背景に、法令に適合した危険物倉庫の需要が急速に拡大しています。安全性確保の観点からも、信頼できる保管環境の確保が重要な経営課題となっています。

危険物倉庫を選ぶ際のポイント
危険物倉庫を選定する際は、まず対応できる危険物の類別と数量許可を確認することが前提です。加えて、危険物取扱者資格を有するスタッフの常駐体制、定期点検や防災訓練の実施状況、入出庫時の記録管理体制など、運用面の仕組みが整っているかが重要な判断基準となります。さらに、防爆照明・換気・消火設備などの安全設備が適切に維持されているか、そして立地面でのBCP対応力(災害リスク分散や広域配送への適性)も選定のポイントです。これらを総合的に確認することで、安全かつ効率的な危険物保管体制を構築できます。

まずは以下までお声がけ下さい!1営業日以内に担当より御連絡差し上げます。
SBS東芝ロジスティクス(株)
営業戦略部
TEL:050-1741-3075
(土日祝を除く AM9:00~PM5:00)